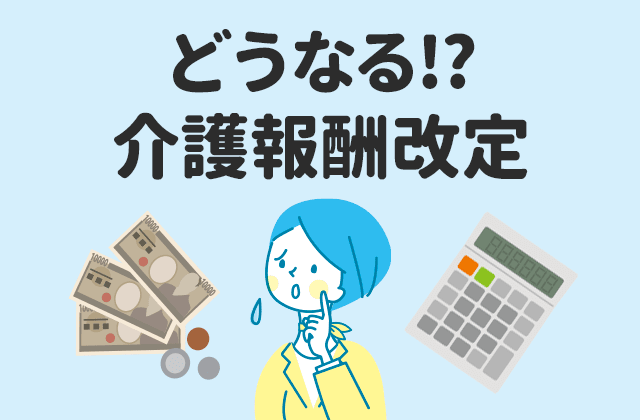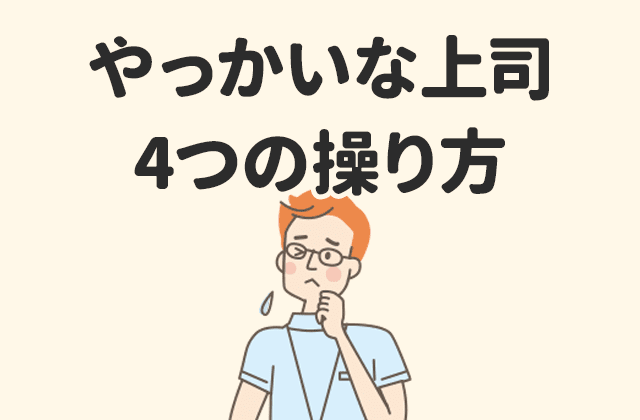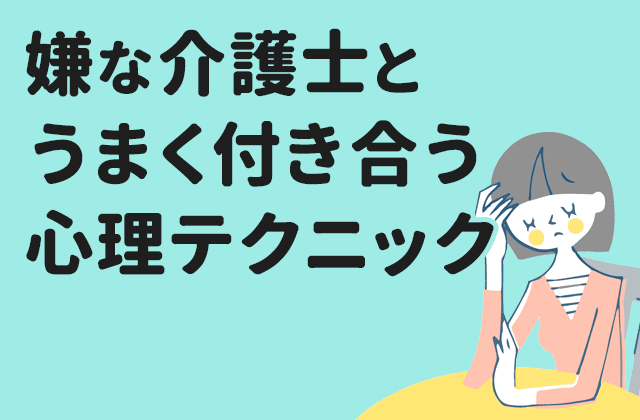ケアマネは今後どうなるの?AIの影響は?現ケアマネや志望者が把握すべきキャリア選択肢

2000年の介護保険制度の創設以降、ケアマネジャーは介護保険サービスを担う重要な役割を果たしてきました。
その一方で、待遇に見合わない仕事内容や責任などから、離職率が高い職種でもあるケアマネ。夢と希望にあふれてケアマネジャーになったのはいいけれど、実際に働いてみると、
「自分が思い描いていた仕事とは違う...」
「もっとやりがいを感じると思っていたのに...」
「こんなことなら辞めたい...」
理想と現実のギャップに悩む人も少なくないといいます。
しかし
「ケアマネを辞めたあとはどうしよう?」
「どんな転職先があるだろう?」
など離職後のことは不安になりますよね。
今回は、ケアマネを辞めたいと思った時にどうすれば良いかをご紹介したいと思います。
「ケアマネを辞めよう」と決断する前に参考にしてみてくださいね。
1. ケアマネを辞めたくなる理由とは!?
まずは、ケアマネを辞めたいと思う主な理由を何点か挙げていきます。
1.1. 本来やるべきケアプランが組めない?理想とのギャップ
ケアマネジャーの大きな役割は、利用者の問題を解決できるようケアプランを作成し、それに基づき支援していくことです。しかし、利用者の抱える問題はさまざまで、中には個人や制度では解決が困難なケースもあります。例えば利用者や家族との意見の違い、介護保険の制約や経済状況などにより、本来やるべき支援をプランに組めないケースもあります。
ケアプランは、ただ単に本人や家族の希望のみで作成できるものではありません。介護保険制度の枠の中で、利用者のさまざまな課題や状況をふまえ作成するという複雑なものなのです。
また、施設や事業所の人員基準で1人のケアマネジャーが担当する件数は決められています。施設や事業所によって差はありますが、ひとりのケアマネがたくさんの利用者を抱えることも少なくありません。そのため担当する利用者の数が多すぎて、じっくりと本人の問題に向き合えないという実態もあります。
1.2. 増える仕事量と残業
ケアマネジャーの仕事は
- ケアプラン作成
- 利用者や家族への相談
- 申請作業
- サービス事業所との連絡調整
- 給付管理
など多岐にわたります。このように、多くの仕事をひとりのケアマネが抱えているため、その対応には膨大な時間と労力がかかります。さらに、ケアマネジャーは利用者の入院や事故など緊急時の際も、迅速な対応が求められます。場合によっては休日出勤をすることもあるでしょう。残業においても、月初めや月末など忙しい時期などは、1日あたりの残業時間が3時間以上というケアマネもめずらしくありません。
給与面では、比較的高収入といわれるケアマネですが、責任や仕事量も多く激務の割には賃金が見合わないという声も少なくありません。
また、相談支援業務というのは利用者や家族から感謝されることはありますが、目に見えて業績が目に見えて上がるというものではありません。心身をすり減らし業務を行っても、自分にかえってくるものは少ないため、モチベーションを保つのも難しく疲れ果ててしまうケアマネも多いのです。
1.3. 現場からの冷たい視線?介護現場との意識のズレ
ケアマネジャーは、利用者の受けるサービスが総合的に行われるようチームケアをまとめる役割です。そのため、サービス事業者や他職種をまとめ、連携を図っていかなければなりません。
ところが、この連携がうまくいかないとケアマネが孤立してしまうケースもあります。本来、ケアマネジャーの役割は現場で「介護」を行う人ではありません。 実際に利用者と密に関わり介護しているのは現場のスタッフです。
そのため現場との連携がうまくいっていない場合、ケアマネと現場のスタッフとの間にズレが生じることもあります。
例えば、ケアマネが立案したプランに対して、現場のスタッフが「実際の利用者の状況とプランが合っていない」「現場の激務でこのプラン実施は難しい」など意見の相違から受け入れてもらえないことがあります。利用者によりよい介護サービスを提供するためには他職種との連携は必須です。
しかし、このようにサービス事業者や他職種の協力が得られず孤立してしまうケアマネも少なくありません。
1.4. AIにケアマネジャーが乗っ取られる?将来への不安
近年、人工知能(AI)を活用しケアプランを作成する試みが民間企業などによって行われています。利用者のデータを学習したAIにケアプランを作成させるというもので、現在、厚生労働省が実用化に向けその実態調査を行っています。
AIをうまく活用できれば、プラン作成時間が縮小され、ケアマネが利用者と向き合う時間が確保できるようになります。業務の負担軽減を図ることができ、AIがケアマネにもたらす利点は大きいといえます。
しかし、厚生労働省が想定するAI活用はあくまで「ケアプランの作成支援」。AIはあくまでもケアマネをサポートする役割です。ケアプランは介護保険のデータだけでなく、本人や家族の気持ちも反映して作成していくもの。ケアプラン作成のすべてをAIが行うことはできません。
ケアマネジメントの主役はあくまで「人」です。
ですから現時点では、AIによって「ケアマネジャーの仕事が乗っ取られる」ことはなさそうですので安心してくださいね。
1分で登録OK
ケアきょう求人・転職の無料相談2. ケアマネジャーを辞めた人はどこに転職する?転職先との給与の比較
介護保険の中核を担うケアマネジャーは介護・医療・福祉の幅広い知識をもつ専門職。
活躍の場も広く仕事内容も多彩です。また、ケアマネジャーは専門性が高い資格であり、今まで培った経験や知識が高く評価され転職に有利となるでしょう。
ここからは、ケアマネにはどんな転職先があるのか?また転職先の給与などをみていきましょう。
2.1. ケアマネとして他の職場に転職する
居宅ケアマネ・施設ケアマネ
ケアマネジャーといっても業務内容は勤務先によってさまざまです。
居宅系か施設系かによっても仕事内容や仕事量はそれぞれ変わってきます。
| 在籍 | 業務内容 | |
|---|---|---|
| 居宅ケアマネ | 居宅介護支援事業所 | 事務業務と外出業務 |
| 施設ケアマネ | 介護施設 | 施設内での利用者との面接など |
しかし、施設によっては、ケアマネ業務のほかに介護業務を兼任するケースもあります。
兼任はシフトで夜勤に入る場合もあり変則勤務となります。そうなると体力的にも負担が増えるので激務になる可能性があります。比較的大規模の施設だと担当する利用者も多いため、ケアマネ業務専任となることが多いようです。
給与面では、居宅であっても施設であっても、経営母体によって大きく左右されます。待遇面でも事業所によってそれぞれで差があるのが実情です。
また、看護師や介護福祉士などの資格を有しているケアマネも多く、保有資格によって資格手当てや夜勤手当などの額も変わってきます。
ケアマネの平均月収は20万~35万程度となっています。年収にすると賞与を含め300~400万円くらいが一般的です。
施設ケアマネで兼任の場合は、介護職と同じく夜勤手当などが加算されるため、総支給額が高くなる傾向があります。そのため、施設ケアマネのほうが居宅ケアマネより給与が高いケースが多い ようです。
このようにケアマネとして働く場が、居宅か施設かによっても業務内容や待遇なども違ってきます。
自身の希望や経験、ライフスタイルなどを加味し、居宅から施設ケアマネとして、もしくは施設から居宅ケアマネとして再スタートしてみるのも選択肢の一つといえるでしょう。
大規規の事業所に転職
給与面で離職を考えているなら、大企業のケアマネとして転職してみるのもいいかもしれません。大企業が経営している事業所は大規模で基盤もしっかりしており、給料は比較的高く安定しています。
| 規模 | 10人から99人 | 100人から999人 | 1000人以上 |
|---|---|---|---|
| 平均年収 | 371万円 | 380万円 | 387万円 |
パートタイムで働く
ケアマネジャーは常勤だけでなくパート(非常勤)としての働き方もあります。
パートタイムのケアマネジャーの時給は1200円~1500円程度となっており、高時給で優遇されているといえます。パートタイムは短時間勤務や週数日の勤務も可能な求人もあり、ライフスタイルに合わせ比較的負担の少ない働き方ができます。
介護認定調査員
今まで培った豊富な知識や経験を活かし、介護認定調査員としての働き方もあります。
介護認定調査員は要介護認定を受ける方の自宅などに訪問し、調査項目に従って聞き取り調査を行います。要介護度を決定する資料を作成するという重要な仕事です。
介護認定調査員になるには、市区町村や自治体が行う研修を受講することで調査を行う資格が得られます。主な勤務先は市区町村の介護保険課や社会福祉協議会などになります。
地域によって差はありますが、月給は15万~20万程度となっています。
勤務形態や給与面は勤務先によって大きく変わってくるようで、時給制や日給制、訪問調査1件につき○○円と件数によって支払われる場合もあります。
2.2. 現場の介護職
介護職から、ケアマネにキャリアアップする人は多いと思います。
しかし、いざケアマネになってはみたものの、ケアマネと介護職の仕事内容などにギャップを感じることがあるかもしれません。ケアマネは相談支援がメインの仕事ですが、やはり現場の介護職のように、利用者と密に関わり支援がしたいと思うこともあるでしょう。
その場合は介護職として復帰してみるのも良いかもしれません。
ところが介護職はケアマネより給与が低いのが一般的です。
| ケアマネ | 介護職員 | |
|---|---|---|
| 平均月収 | 20万~35万円 | 17万~27万円 |
しかし、近年では国も介護現場の人手不足を解消するために、介護職員の待遇改善に取り組んでいます。 厚生労働省は2019年10月にベテラン介護福祉士らの処遇改善に向けて新加算を創設する方針を決定しました。
これはベテランの介護福祉士を中心に、事業所側が認めれば恩恵を受けられるというものです。施設や介護事業所で働いている「経験・技能を持つ介護職員」が対象です。
新加算によって事業者が得た増収分については主にベテラン介護職員(介護福祉士)の給与アップにつながるよう配分していくというものです。ちなみにこの新加算は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーは対象外となっています。
新加算の導入で今後、ケアマネより給与面で優遇される介護職員が増えると予想されます。近い将来、ケアマネと介護職員の賃金が逆転することもあるかもしれません。
ここでは、介護職への復帰について述べてきましたが、もちろん、自身のバックボーンが介護職以外なら、その分野への復帰も転職の選択肢のひとつです。
2.3. 福祉業界の他職種にチャレンジ
専門性の高い知識を有し、介護現場での経験が豊富なケアマネジャー。
活躍の場はケアマネだけの職種にとどまりません。
今までの経験を活かして、介護講座などの講師としての働くこともできるでしょう。また、福祉用具相談専門員として働くこともできます。
福祉用具相談専門員は、利用者の福祉用具の選定、納品、設置、説明、モニタリングなどを行います。ケアマネはもちろんのこと介護福祉士や看護師などの有資格者はさらに給与が高くなるようです。
| 介護講座などの講師 | 福祉用具相談専門員 | |
|---|---|---|
| 給与 | 時給1500円~3000円 | 月給15万~25万円 |
| 勤務先 | ・介護講座などを実施しているスクール ・福祉系専門学校 |
・福祉用具を扱う民間企業 ・レンタルやリースを行う会社 |
3. ケアマネを辞めた人が気を付けるべきこと
3.1. ケアマネへの復帰可能性
もし、ケアマネを辞めて違う職種に就いても、「やっぱり、またケアマネとして働きたい!」と思うことがあるかもしれません。高齢化社会にともないケアマネの求人数は多く、今後も重要度が高い仕事といえるでしょう。資格はありますのでケアマネ業務に復帰することは可能です。その際は、資格の有効期限が切れていないか確認し、切れていた場合は更新の手続きを行って下さい。
3.2. 資格の更新
ケアマネジャーは5年ごとの更新制の資格です。
復帰の際、更新手続きをせず有効期限がきれてしまうと、すぐにケアマネ業務に就くことはできないので気をつけましょう。
復帰の際は有効期限を確認し、必要な場合は必ず更新研修を受講して更新の手続きを行って下さい。更新研修は各都道府県が実施しています。研修の日程などの詳細は各都道府県に事前に確認して下さい。
4. まとめ
ケアマネを辞めたい理由は、給与、仕事内容、人間関係など、人それぞれだと思います。
もしこのまま無理をして、体力的、精神的に参ってしまうなら、その前に辞めるという選択も大切です。
しかし、いざ転職をするとなると迷いや不安もありなかなか一歩を踏み出せないこともあるでしょう。
そこで大切なのがもう1度いろいろな角度から自分を見つめ直してみること。
今仕事を辞めたい理由は何なのか?自分がやりたい仕事は何なのか?
それが明確になると、おのずと目標も見えて転職の道も開けるでしょう。
自分にとって良い退職・転職ができるように、将来に向け一歩一歩、進んでみてくださいね。
1分で登録OK
ケアきょう求人・転職の無料相談